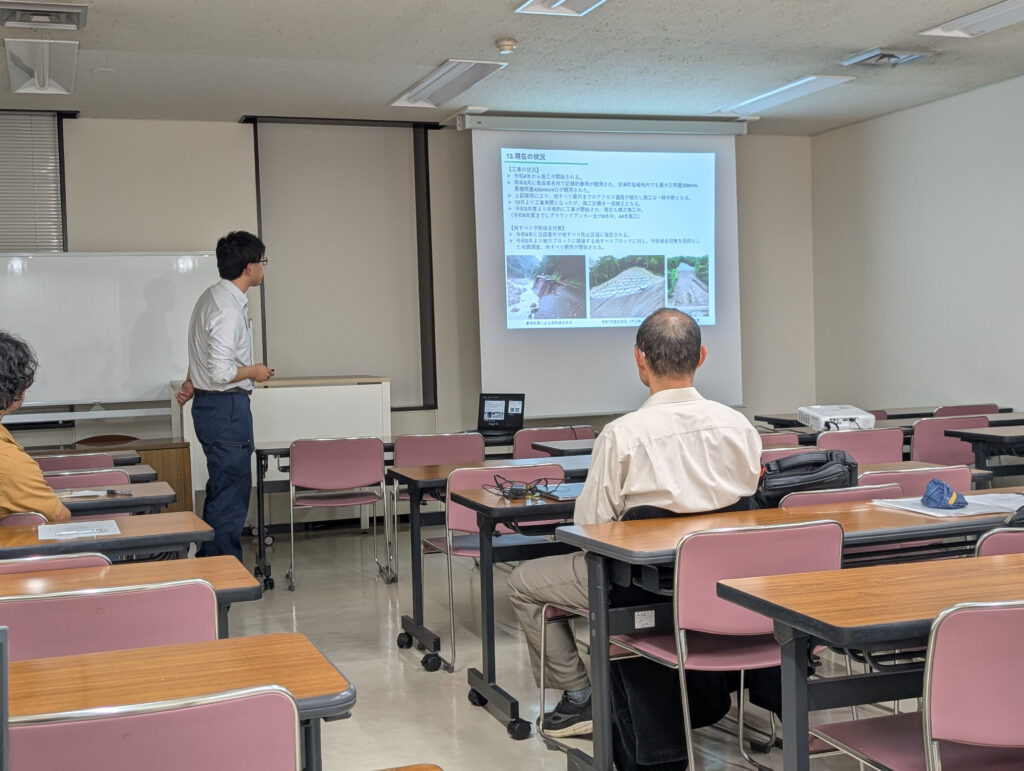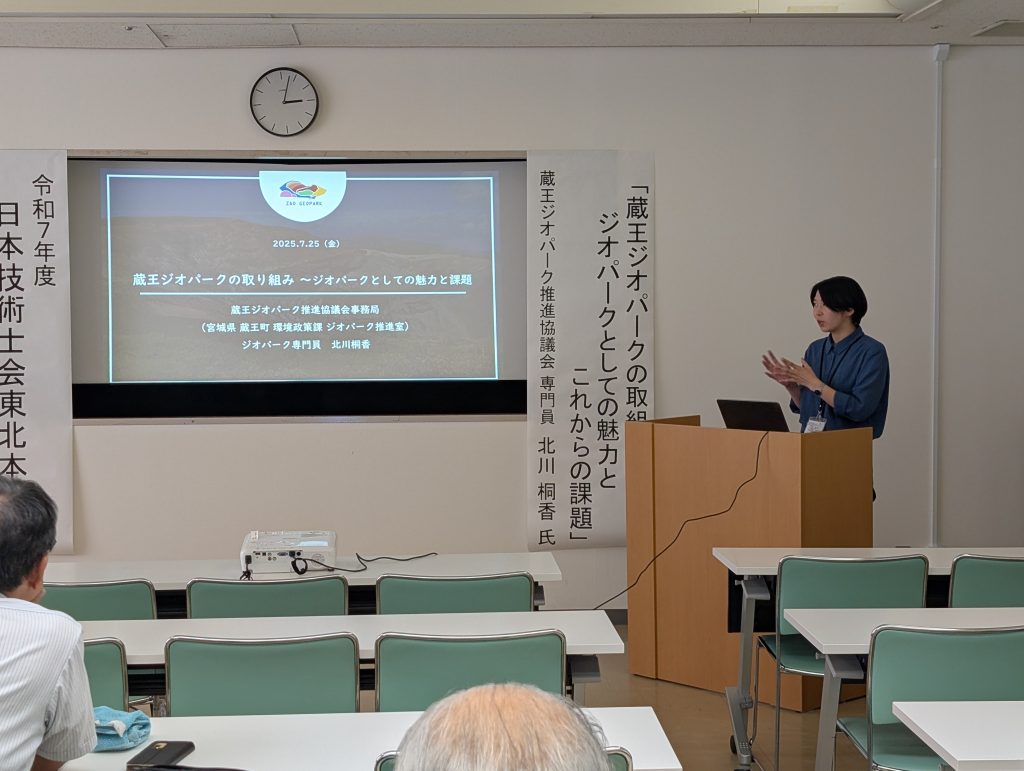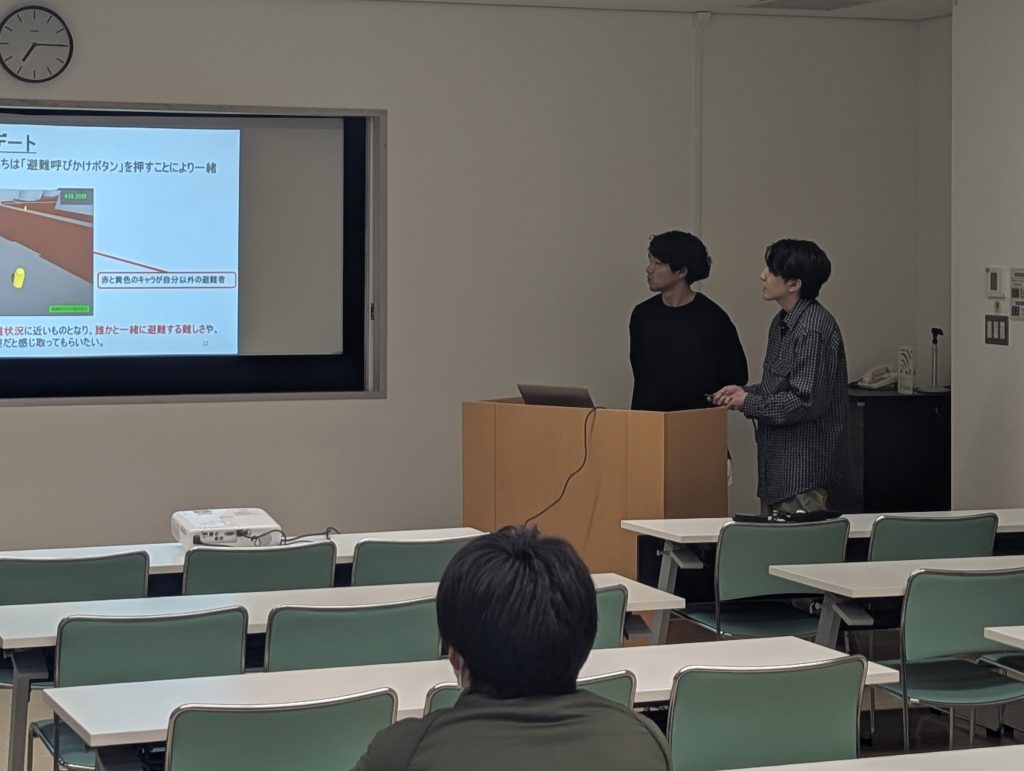令和7年9月17日(水)「蔵王ジオパーク見学会」を開催いたしました。集合場所は、蔵王町遠刈田地区公民館内の蔵王ジオパークセンターでした。今回は、蔵王火山を始めとした蔵王ジオパークのジオサイト見学が目的です。見学会の案内は事務局に依頼し、案内者は蔵王ジオパーク認定ガイドの田村信幸さんと平間幸子さん、またスタッフの北川桐香さんも同行してくださいました。当初の計画では、午前中に蔵王エコーライン沿いの駒草平(標高約1,350m)と蔵王火山の五色岳(標高1672m)及び御釜や刈田岳山頂(標高1757.6m)の刈田峰神社等を見学する予定でした。しかし、蔵王山ふもとの蔵王町内は晴れていたものの、山頂付近は風速17~18m/秒以上とのことでしたので、駒草平の見学だけでもと現地を目指して出発しました。
駒草平に到着すると、幸いなことにそれほど強風ではなく、ガイドの田村さんの説明を聞きながら周辺を見学しました。次第に強風にはなりましたが、夏には綺麗に咲いていた駒草や地表を覆っているアグルチネートや対岸の火砕岩露頭をを観察することができました。また、今年で無くなるという展望台からは不帰の滝、終了間際には雲間からカルデラ湖内の水中火砕岩と推定される「ロバの耳岩」も遠望することができました。
駒草平からふもとの遠刈田公園に移動し、公園内の「岩崎山金山跡」を見学しました。岩崎山金山は金、銀、銅を含む鉱山で、鉱脈沿いにたぬき掘りで採掘された坑道入口が確認できました。江戸初期には伊達政宗の支配下にあったとのことです。次に県道12号(白石上山線)を挟んでサン・スポーツランド西側に隣接する空き地に移動し、「遠刈田製鉄所高炉跡」を見学しました。明治時代に完成した遠刈田製鉄所は、鉄鉱石の入手難や資金不足により、稼働しないままに解体・移設され、レンガ製の基礎部のみ確認できました。
午前中最後の見学地は、澄川・濁川合流点でした。澄川は屏風岳や芝草平周辺から森林地帯を流下する清流ですが、濁川は御釜周辺から火山地形内を流下する酸性の川です。この地で合流した河川水はやや緑がかった色でした。光の当たり具合によっては、御釜と同じエメラルドグリーンの色調になるとのことでした。
昼食は、近くのそば処で「とうふづくし」のコースを味わいました。
午後の最初は、「蔵王町ふるさと文化会館(ございんホール)」内の「谷地遺跡」に関する展示物の見学でした。「谷地遺跡」は平成23・24年度の発掘調査の結果、縄文時代中期前半(約5,500~5,000年前)の大規模な集落跡であることが判明したとのことです。竪穴住居跡の写真や発掘された土器・石器等が数多く展示されていました。次に、ございんホールから高台の展望地に移動し、松川河岸段丘を望みました。この展望地は松川左岸の「永野段丘面」上に位置し、先ほどの「谷地遺跡」は松川左岸の下段「矢附段丘面」上にあったとのことでした。
最後の見学地は、円田盆地で「産直市場みんな野」の駐車場付近から周辺地形を遠望しました。円田盆地は白石カルデラの一部であり、白石市北部~青麻山~松川中流域~円田盆地にかけての巨大カルデラとのことです。また、円田盆地周辺からは、かつて、湖であったことの痕跡として珪藻土層が分布しているとのことでした。説明を聞いた後、蔵王町で今、旬の果物である梨を多くの参加者が購入しました。土砂降りということもあり、ジオパークセンターに戻って解散することにしましたが、移動中に雨が上がったタイミングであきらめていた「疣(いぼ)岩分水工」に立ち寄っていただきました。澄川・濁川合流点付近にある遠刈田発電所で発電用に使用した水の一部をこの「疣岩分水工」に導水し、かんがい用の澄川用水路と黒沢尻用水路に分水しているとのことでした。ここが本当に最後の見学地となり、ジオパークセンターに戻って挨拶後に解散となりました。
蔵王ジオパーク見学会には総勢10名に参加していただきました。